2026年8月の税理士試験に向けて、国税徴収法の勉強を開始することにしました。
なぜ国税徴収法なのか
税理士試験の選択必修科目の中で、国税徴収法を選んだ理由はシンプルです。比較的ボリュームが少なく、理論と計算のバランスが取りやすい科目だからです。税法科目の入門としても適していると判断しました。
独学という選択
今回、予備校の教材は基本的に使わないことにしました。
理由は主に3つあります。まず、自分のペースで学習を進めたいこと。次に、過去問を徹底的に分析することで出題傾向を自分なりに把握したいこと。そして、費用面でも独学の方が負担が少ないことです。
もちろん、予備校には体系的なカリキュラムや講師のサポートという大きなメリットがあることは理解しています。しかし、今の自分には過去問中心の学習スタイルの方が合っていると考えました。
ただし、一部予備校の教材を使っての勉強も実施します。というのも、国税徴収法は理論の暗記が必須になります。大手の予備校が出している理論暗記用のノートを用いて、暗記を進めながら過去問の演習も進めたいと思います。具体的には、TACの理論マスターを使うことにします。
具体的な学習方針
勉強の中心は過去問演習です。
まず、直近10年分の過去問を入手し、出題パターンを分析します。最初は解けなくても構いません。問題文を読み、何が問われているのかを理解することから始めます。
基本書は市販のものを1冊用意し、過去問で分からない論点が出てきたときの辞書として使います。あくまでも過去問が主、テキストが従という位置づけです。
理論問題については、過去問で頻出の条文から順に暗記していきます。計算問題は、パターンを体に染み込ませるまで反復練習します。
今後の予定
8月の本試験まで、約1年間の長期戦です。
最初の3ヶ月は基礎固めの期間として、過去問を解きながら全体像を把握します。年明けからは本格的な演習期間に入り、5月のゴールデンウィーク明けからは総仕上げに入る予定です。
途中で方針転換が必要になるかもしれません。独学の限界を感じることもあるでしょう。それでも、まずはこの方法で挑戦してみます。
最後に
税理士試験は難関資格として知られています。特に働きながらの受験は、時間的にも体力的にも厳しいものがあります。
それでも、一歩ずつ前に進んでいきます。来年の今頃、良い報告ができることを目指して。
勉強の進捗については、このブログで時々報告していく予定です。同じように資格試験に挑戦している方、これから挑戦しようと考えている方の参考になれば幸いです。

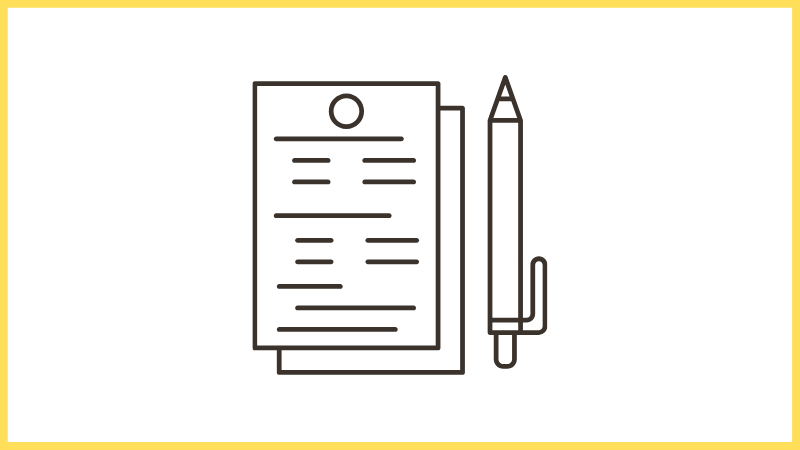
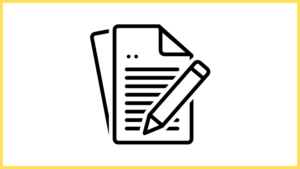

コメント